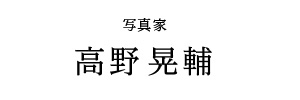カント峰(7055m)への想い
私が登山を始めた動機は、ヒマラヤの未踏峰の頂に立ちたいというものだった。中学三年生のとき、日本の登山隊が世界第二の高峰K2の第二登を果たした。そのドキュメンタリーをテレビで見たとき、雪をまとってそびえ立つK2の神々しい美しさに目を奪われた。その頂に向かって胃液を吐き続けながら登るクライマーがいた。なぜそこまでして頂上を目指そうとするのか、その頂上に何があるのか知りたいと思った。その頂が未踏峰で世界で初めてそこに立った瞬間にはどんな気持ちになるか味わってみたいと思うようになった。
ヒマラヤの未踏峰に初登頂という夢を叶えるために、大学で体育会山岳部に入った。毎日ハードなトレーニングをこなし、入山日数は多い年で、一二〇日を超えた。一年生のときは、登山の全てが新鮮で、山行中は雨に濡れても着替えず着干しで乾かすことなどに驚いた。山は、激しく変化する気象、突然襲ってくる落石や雪崩などの危険に満ちている。気を抜くと死に直結する場合も少なくない。長期山行の出発前は、部屋の掃除をして、覚悟を決めて家を出た。
無事に下山したときは、生きているという実感とよろこびが体中に充満することもあった。
そんな山の恐ろしさを、一年生の冬山で味わうことになった。雪崩に襲われ、パーティ九名全員が雪に埋まったのである。雪の中から自力で脱出したものが、体の一部が見えているものを掘り出して七人救出。私を含め残り二人の捜索活動がはじまった。そのとき私は三十分埋まったままで、生きることを諦めて死を覚悟した後に、酸欠により意識を失っていたが、奇跡的に掘り出された。
最後に一人だけ、雪深く埋まったまま救出できなかったのが同学年の石部正彦であった。
とてもつらい体験だった。この時の自分を支えたのは、亡き友と「一緒にヒマラヤの未踏峰を登ろう」と交わした誓いと、ここで止めたら自分が駄目になるという気持ちだった。それから、さらに強くなった未踏峰への想いと共に、山を登り続けた。
そして、目標が実現するときがやってきた。石部の死から四年、一九八六年六月にチベットの秘峰カントの登山許可が中国政府からおりた。カントはブータンの東、未知のつまった魅力的な地域にそびえる未踏峰である。世界的に知られている山であるが、写真が一枚も発表されていない幻の山であった。この山はOBの宮崎が九年前から目指していた山である。私も宮崎から話を聞き、カントという未踏峰にロマンをかき立てられていた。
その年の秋に、私を含めた、宮崎をリーダーとする四名の偵察隊が、二ヶ月にわたってカントの内院深く入り登路を探った。初めて目の当たりにしたカントは大きな全身に雪をまとい、頂上付近に雪煙を巻き上げていた。その姿を見て、夢がまさしく手に届くとこまできてるのを感じた。
二年後の一九八八年三月五日、ベースキャンプを建設した私たちは本格的な登山を開始した。三パーティ構成でルート工作と荷揚げを行うのだが、私は宮崎のパーティに組み込まれ、主にルートを切り開くというポジションに恵まれた。
このとき私は、「なぜ山を登るのか」を写真で表現していくために、プロの写真家を目指していた。撮影にも真剣に取り組んだ。カメラとレンズはマイナス五十度でも耐えられるように改造をしてもらった。高所登山ではグラム単位で軽量化して登攀の効率化をはかるものであるが、標高五◯◯◯メートルを超える高所でも三キロの撮影機材を持ち、常に首からカメラをぶら下げていた。
アタックを翌日に控えた最終キャンプの夕方、後輩の高須がコッフェルをひっくり返し、沸騰したスープが私の足の甲にかかった。急いで冷やすが、ひどい火傷ならば、明日のアタックは諦めざるをえない。自分を責める高須に「俺がだめでも、お前が頂上に立てればそれでいい」となぐさめる。不思議とこのまま下山してもそれを運命と素直に受け入れられる気がした。
三月二十四日アタックの朝、私の足は火傷で腫れていなかった。神に感謝して急いで出発準備をする。登山の朝は一秒をあらそう修羅場だ。午前七時五十分に私と高須が先行した。
予定通り固定ロープを四本張り終え、六九◯◯メートル地点で宮崎と佐藤を待つ。まもなく宮崎は追いついたが、佐藤がなかなか来ない。足どりが重そうである。ようやく合流した佐藤にリーダーは下山を命じた。このペースでは登頂どころか、むしろ危険と判断したようだ。その佐藤に高須を付き添わせた。
この日の高須の体調は非常によかった。私は足が重く、好調とはいえない。しかし、ここまで来たからには「どうしても自分が初登頂を遂げたい」という思いを胸に、押し黙っていた。茫然とする高須にカメラを向け、やり場のない憤りを込めてシャッターをきった。「おまえの分まで頑張ってくるからな」と叫んで、登りはじめる。
七◯◯◯メートルを超えるあたりから、横殴りの西風が吹きつけてきた。秒速二◯メートルの風に気温はマイナス三◯度、体感温度はマイナス五◯度にもなる。強風のため呼吸がしづらい。ますます体が重くなり、ペースが落ちる。とにかく、遅くとも休まず歩みを進めることに専念する。颯爽と登れない自分に怒りと悔しさが込み上げてきた。
頂上が二◯メートル先に迫ったとき、後ろを振り返り、「宮崎さん、十年来の恋人でしょう、先に行って下さい」と初登頂を譲ろうとした。「しょうもないこといってないで、早く行け」というのが宮崎の答えだった。「宮崎さんらしいな」と納得して、再び登りはじめた。「もう少し」と力をふりしぼってスピードを上げると、頂上から二、三歩通りすぎてしまった。振り向くと、ピークに宮崎が立っていた。「宮崎さん、そこがピークです」と叫んだ。
固い握手をする。宮崎は南を見やり、十一年前にこの山を遠望したアッサムのブラフマプトラ河岸に思いをはせているようだ。「石部のためにも、いい山登りをしよう」と誘ってくれた宮崎に、ただ「ありがとうございました」とだけ言った。「ようがんばった」と宮崎が行った瞬間に、涙がボロボロとあふれた。遭難後、どこの山へ登るときも石部の写真は肌身はなさず持っていた。「一緒にヒマラヤの未踏峰を登ろう」という石部との誓いを、いま果たしたような気がした。
このとき、宮崎は十年来の目標を成し遂げ、私はヒマラヤの未踏峰に初登頂するという夢を叶えた。しかし、私たちには湧きあがるような感動はなかった。
初登頂に成功し、第一キャンプに帰ったのは午後八時を過ぎていた。全隊員が心から登頂を祝福してくれた。無念の涙をのんで下山した高須が私に抱きついて泣き出した。みんながこのキャンプで迎えてくれたときが、いちばん嬉しく感動した最高の瞬間だった。
帰国後しばらくして、「カント峰初登頂おめでとうございます。故人のやり残した想いもこれで区切りがつけれると思い、ようやく墓を建てました。」というハガキが石部の父親から届いた。
亡き友に誓ってまだ果たしていないことが、もうひとつある。「なぜ山を登るのか」を表現した写真集『登魂』を発行することである。
高野晃輔
<日本広告写真家協会(APA)発行『APA NEWS No.86 』2004年10月号掲載>